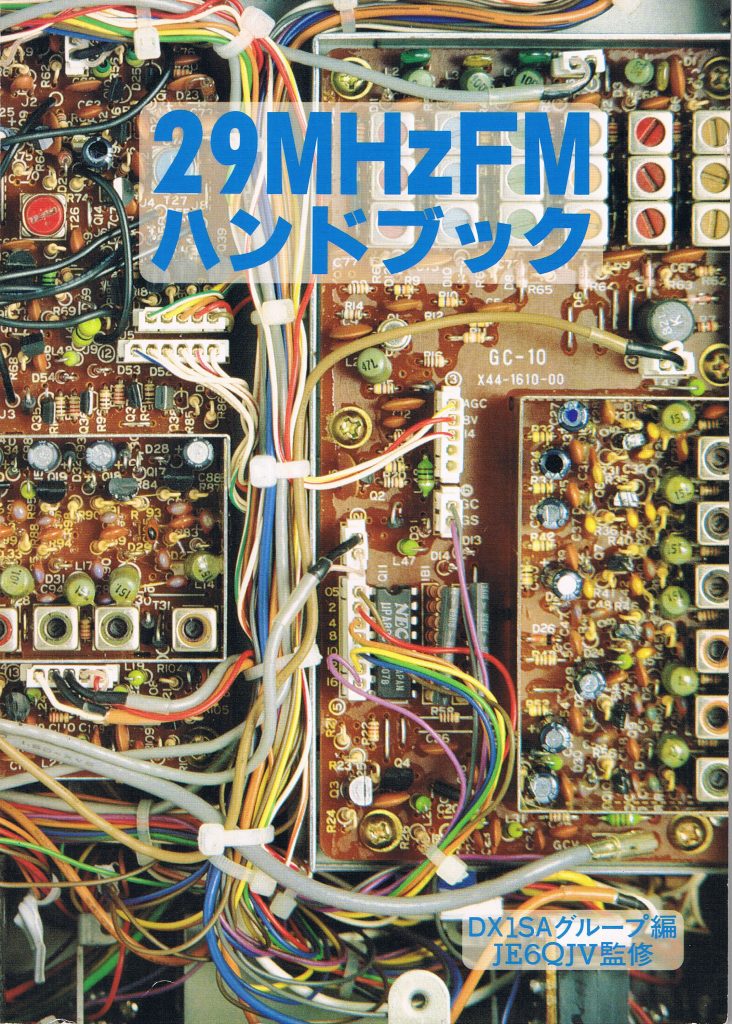無線ブログ集
| メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示

 JG6DMH・ふくおかNX47のブログ
(2026/1/9 7:35:10)
JG6DMH・ふくおかNX47のブログ
(2026/1/9 7:35:10)
現在データベースには 210 件のデータが登録されています。
 久留米特小レピーター復旧
(2020/9/17 6:32:27)
久留米特小レピーター復旧
(2020/9/17 6:32:27)
強烈な台風10号が来るというので、前のブログ通り高良山のレピーターを撤去しました。その際、ソーラーパネルまわりの劣化がひどく、新調することにしました。
ソーラーパネルと架台をここから注文。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kausmedia/
ところが、ソーラーパネルと架台のネジ穴が合わない。片方だけ合わせても、電源部分にひっかかってしまう。

説明書を良く読むと、何と、両面テープで貼り付けろとある。不良品かと思っていたが、そういうことだったのね。失礼しました。
しかし、10年はもたせようと考えているのに、両面テープのみでは心もとない。ということで、ソーラーパネルに穴を開けてネジ止めすることにした。

いい加減な作業なので、やりかぶる(失敗する)ことが多い。で、今回の失敗は、穴が貫通して下のソーラーパネル部分までドリルで傷つけてしまった。ちょっと敷物でもしておけばいいのに。
テスターで当たったら、0V。チーン お亡くなりになった。
やっちゃった。まぁ、安いからいいか、と涙目の自分に言い聞かせ、何気なくパネル裏のボックスを開けてみた。

何とまあ!どうしたことでしょう! これぞ中華クオリティーなのか。プラスラインが半田付けされていなかった。自由な身であった赤ラインは、はずれてしまっている。テスターで調べると問題なし。どうせ別コードを使うので、既存コードを外して半田し直し。

15日夕方、高良山へ。この場所は許可を得ているところです。(昔の勤務先)
今回は、単管パイプ2本でがっしり固定しました。
今まではアルミの収縮ポールで上に上げていましたが、風でゆらゆら、ゲートウェイとの間でQSBが発生していました。今回は少し低くなりましたが、QSBは無くなると思います。
ちなみにレピーター本体のブログはこちらです。
DJ-R200Dで新しいレピーターを製作
 久留米特小レピーター 揺れてる
(2020/9/17 2:03:54)
久留米特小レピーター 揺れてる
(2020/9/17 2:03:54)
自宅eQSOゲートウェイ=>久留米レピーターのアクセスがQSBあって途切れるので先日様子を見に行きました。強風でユラユラしていました。単管パイプにでも交換必要かなぁ。
自宅eQSOゲートウェイ=>久留米レピーターのアクセスがQSBあって途切れるので先日様子を見に行きました。強風でユラユラしていました。単管パイプにでも交換必要かなぁ。 pic.twitter.com/mfnSinw237
— ふくおかNX47・JG6DMH (@Nx47J) July 20, 2020
 久留米特小レピーター停波
(2020/9/17 2:03:20)
久留米特小レピーター停波
(2020/9/17 2:03:20)

台風10号がとんでもない強さだということで、久留米特小レピーターを撤収しに行きました。

ずいぶん黄色く変色しています。もう何年?

バッテリーは奥まったところに置いています。久しぶりに開けてみましょう。
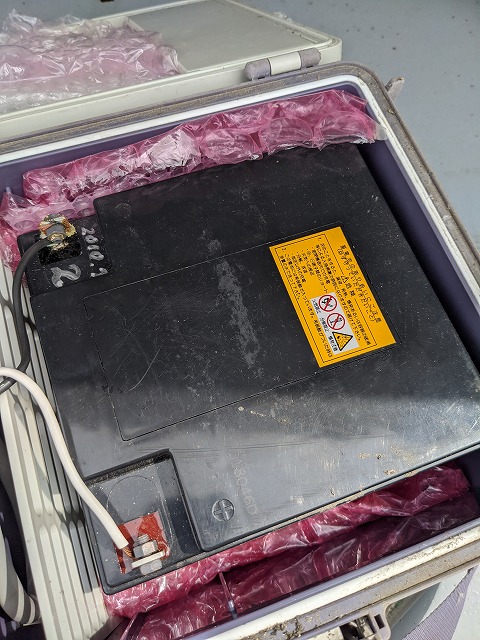
2010の文字が。何とまぁ10年同じバッテリーで稼働中です。ソーラーパネルも同じ。まだまだいけますか。
ありゃ、これはまずいです。棚板の棚板受金具を利用していましたが、錆だらけどころか腐食しています。製作当時のブログがありました。
ソーラーパネル取り付け金具とバッテリー用クーラーボックス
中継器自体は昨年変更しました。
DJ-R200Dで新しいレピーターを製作
今回、ソーラーパネル関係を新調しようと思います。それにアルミポールもぐらつくので単管パイプに変更します。
というわけで、しばらく久留米特小レピーターはQRTです。
 フィリップス369を40ch化できるらしい
(2020/8/13 1:52:03)
フィリップス369を40ch化できるらしい
(2020/8/13 1:52:03)
みつけました。369を”いじくりまわした”方です。
https://www.pa3hjh.nl/?s=369
この中のこの記事のコメント
https://www.pa3hjh.nl/22ap369-40/
いやぁ、グーグル翻訳、役立ちます。
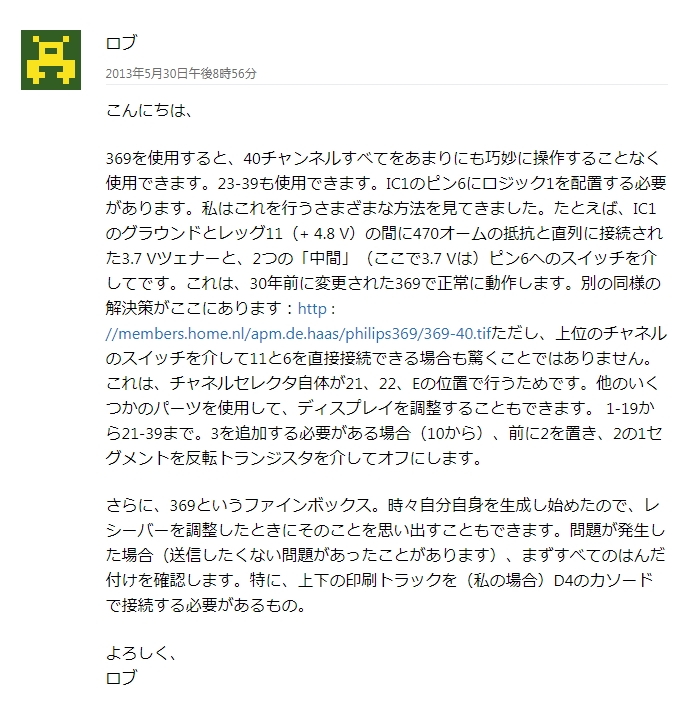
その別の同様の解決策というのがこれ。
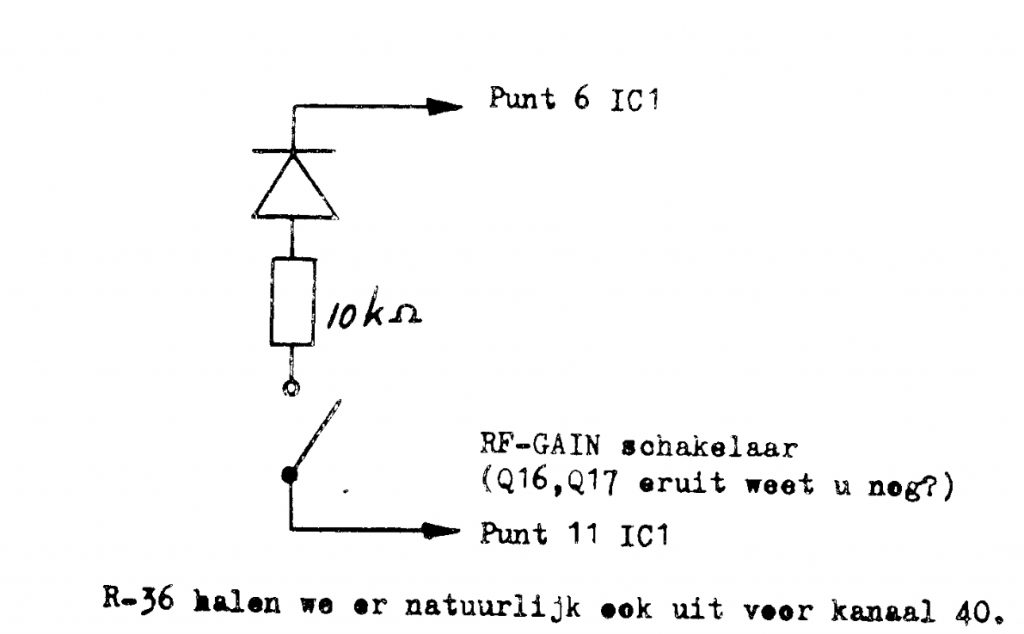
RF-GAINのスイッチは普通使わないので、このスイッチでバンド切り換えしましょう。
R-36 halen we or natuurlijk
ook uit voor kanaal 40
もちろん、チャンネル40にはR-36も使用します
Q16,Q17 eruit weet u nog?
Q16、Q17を覚えていますか?
schakelaar
スイッチ
翻訳しました。
こんなサイトも発見、記録。
http://members.home.nl/apm.de.haas/philips369/
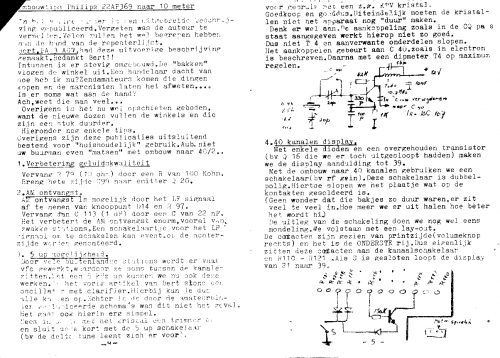
もっと出てきた!
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/gerfeb82.pdf
 27MHz 500mW 22ch FM フィリップス369
(2020/8/11 20:01:13)
27MHz 500mW 22ch FM フィリップス369
(2020/8/11 20:01:13)
27MHz 500mW 8ch AM は日本独自の市民ラジオ。22ch
FMというのはオランダの初期のCB無線の規格だったようです。369でピンときた方は30年以上のベテランに違いありません。フィリップス369、FUJI369とか言ってた方もいらっしゃいましたっけ。
オランダのCB無線機なのであります。そう、フィリップスはオランダの会社です。私の場合、フィリップスは電気シェーバーのイメージが強かったりします。正式には
22AP369 という型番だったようです。

22AP369でググると、オランダの雑誌が出てきました。Radio Bulletin、「現代無線」みたいな感じでしょうか。
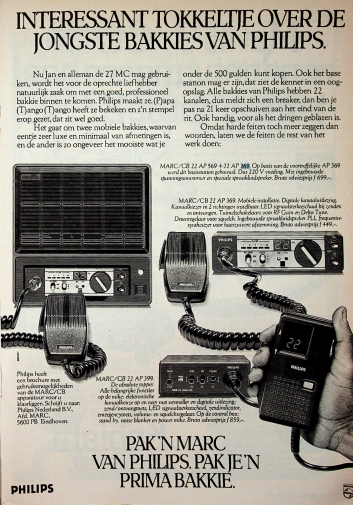
このCBトランシーバー、30年ちょっと前にブームとなりました。10mFMにオンエアできるトランシーバーが少なかった頃、格安で購入でき、29MHzへの改造キットが出たことから人気になったようです。半田ごて握って頑張ったOMさんもいらっしゃるのでは。
※改造記事はアップしたこちらのハンドブックの中にもありました。
https://nx47.com/modules/xpress/?p=1204
秋葉原の富士無線さんが、キットと一緒に販売されていた記憶があります。フィリップスのブランド名は。「FUJI」のシールで覆われていたような・・・
2017年の西日本ハムフェアでの展示。これ以来、探しておりました。
https://nx47.com/modules/xpress/?p=701
検索するとサービスマニュアルがネットにありました。回路図、調整方法全てバッチリ記載されています。ただし、オランダ語のようです。
https://elektrotanya.com/philips_22ap369_14.pdf/download.html
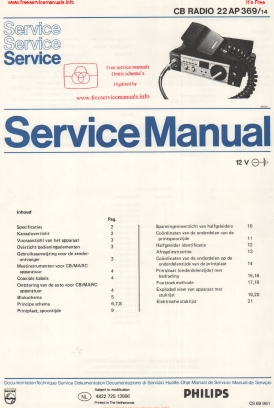

このトランシーバーは10kHzステップでして、いわゆるスーパーナローFMでした。そのため、受信感度いいんです。SGで-137dbmを確認、ノーマルのPCSシリーズより耳が良いです。
出力を測定、およそ500mW出ています。当時は2Wへの改造が盛んに行われていましたが、今回は敢えて500mWのままで楽しみたいと思います。
ちなみに二台購入したうちのひとつがパワー出ず。調べてみるとファイナルが抜かれていました。

改造しようとして、途中でやめたのかな。
このトランシーバーにはチップ部品が使われていません。古いので。勉強の材料には最適です。
 CR8900の収縮チューブ交換修理
(2020/6/4 23:02:34)
CR8900の収縮チューブ交換修理
(2020/6/4 23:02:34)
10mFM用モービルアンテナで最もユーザーが多いと思われるのが、ダイヤモンドアンテナのCR8900です。
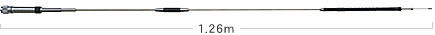
10mバンドのみ上の調整エレメントで周波数を動かすことができます。
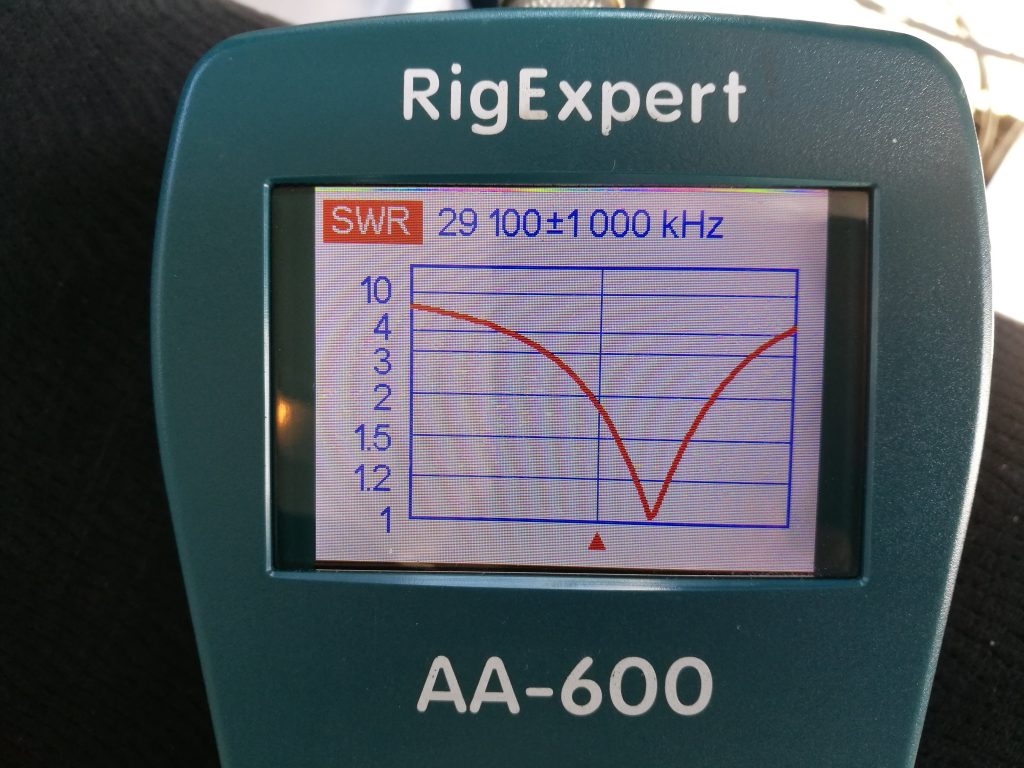
先日、時々29MHzのちょい下でSSBで送信することもあるので、中心を29.10MHz付近に合わせていたのですが、ずれています。しかも調整前の周波数にずれています。なんで?

車から取り外して再調整しようとしたら、コイル部分から水がたれています。そういえばOMさんから水が入ってSWRが高くなった、使っているとそのうち蒸発してSWR下がるんだ、なんていう話を聞いたことがあります。
こりゃ、ヒシチューブの交換ですな。
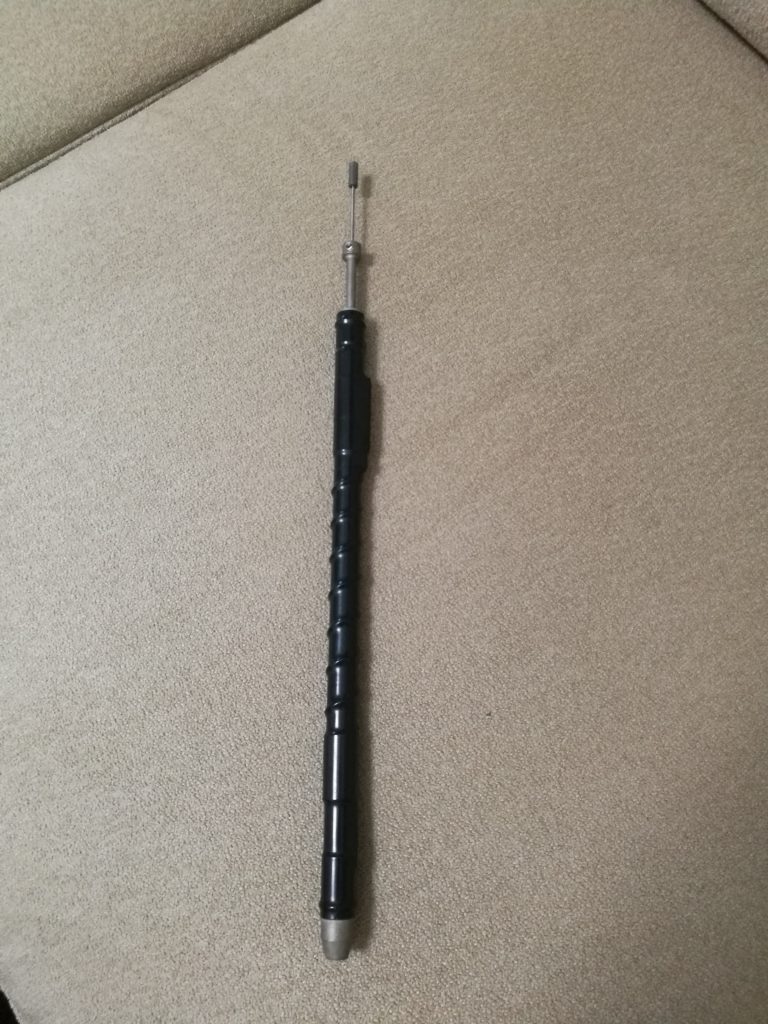

今付いているヒシチューブをはがします。どうやらパイプの中にまで水が入っている様子。お天気いいので車の天井で数時間天日干ししました。ばっちり乾燥。
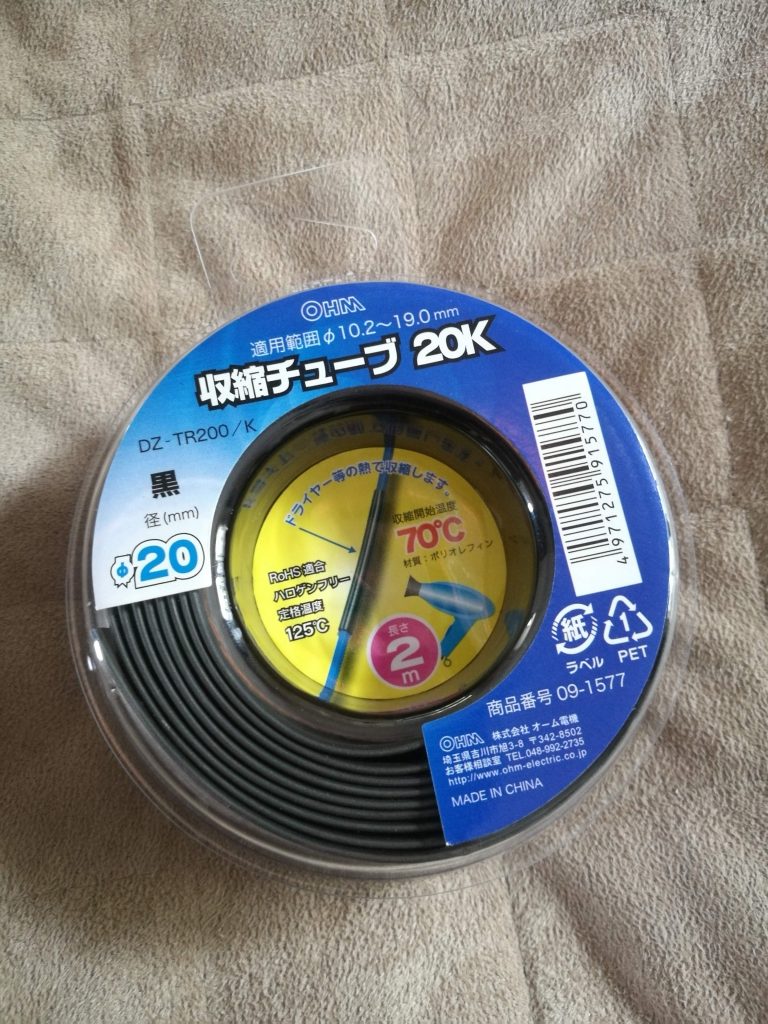
いつものDIY店にはこれしかない。ノギスでコイル部分の一番厚みがあるところを測ったら15mm。15mmのヒシチューブは内径14mm以下みたいに書いてある。悩むなぁ。大は小をかねるというけど、これはそう兼ねません。悩んで結局20mmパイのこれを購入。ちょっとでいいのに、こんな長さ要りませんけどね。
実際、差し入れてみると、でかい。しかも生地が厚い。大丈夫か? 家のドライヤーで熱風を吹きつける。変化なし。おいおい。
こういう時は、極端にやってしまう私。カセットボンベにガストーチバーナーで直接火を。「縮めーーっ」

何とかなったような気はします。ただどうも上部が心配。結局、自己融着テーププラスビニルテープ、末端は接着剤処理。

その後再調整で、OKになりました。そうそうヒシチューブつけない裸の状態だと上に400kHzほど上がっていたような。
このアンテナも消耗品なので、近くもう一本と思っていましたが、せっかく可愛がってあげたので、もう少し遊んでみようと思います。
本当は同じダイヤモンドアンテナの29MHz 144MHz 430MHz
3バンドのモービルアンテナのほうが好みでした。もう作っていません。あれ、型番なんだったけ。倉庫に入っているかも。
 29MHzFMハンドブック
(2020/6/4 22:59:56)
29MHzFMハンドブック
(2020/6/4 22:59:56)
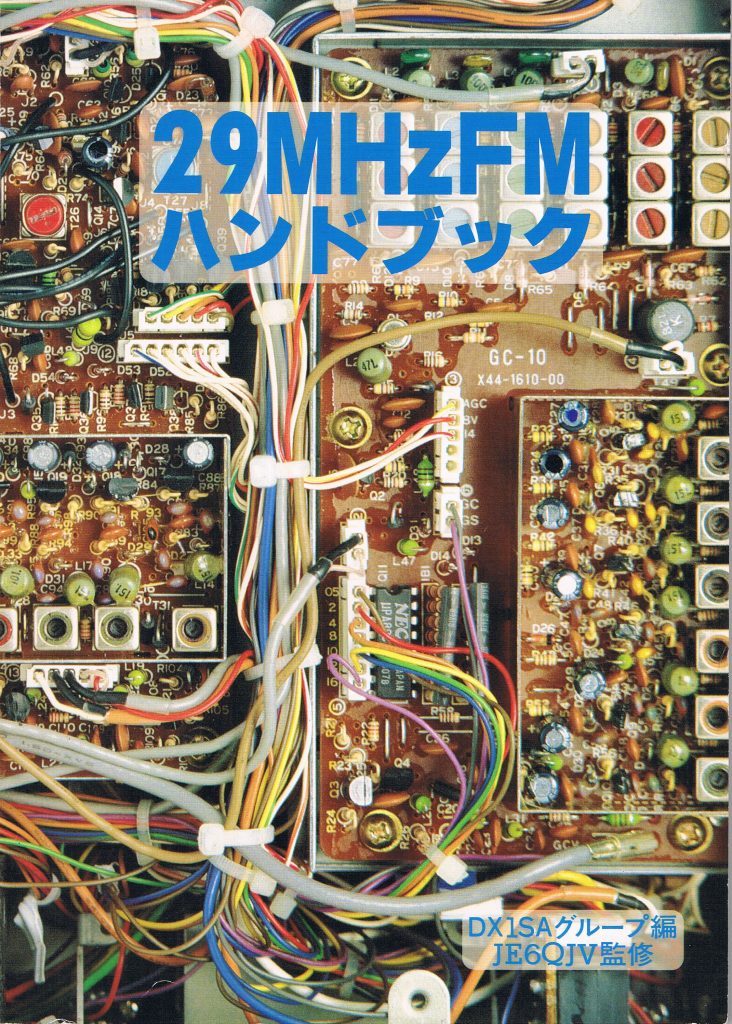
DX1SAグループ編 JE6QJV監修 なのです。
10mFMハンドブックとずっと思っていましたが、勘違いでした。
一昨年の西日本ハムフェアで在庫一掃したのですが、その後もどこそこから出てきたようで、私の元に集められました。
気持ちとしては、本当に欲しい!という方であれば無料で配布したいのですが、無料となるとそういう気持ちが無い人も手を挙げるわけです。そこで、最も適切な在庫一掃方法を検討中であります。
PDF化も予定しています。すぐにでもできるといえばできるのですが、データをどこに置いておくかが問題です。とりあえず当サイトでもいいかもしれませんが。アツデンの取扱説明書、回路図なんかもどこかにアップしておきたいですね。 そうそう、CQ誌のJG1DKJ澤田氏の10mFMコーナーもありましたね。
追記 PDF版をアップしました。
https://nx47.com/modules/xpress/?p=1204
 29MHzFMハンドブック2 PDF版
(2020/6/4 22:12:13)
29MHzFMハンドブック2 PDF版
(2020/6/4 22:12:13)
29MHzFMハンドブック2(DX1SAグループ編 JE6QJV監修)をダウンロード (PDF 26.7MB)
ご期待の声がありましたので、PDF化してアップロードしました。
JE6QJV牧野OMより、予てよりご承諾いただいております。
書名に”2”は付いていないのですが、これが発行された前年にも同名のハンドブックが同グループ編で出ていますので、区別のため「ハンドブック2」とさせていただきました。
 アルインコ電源 EPS-300M 修理
(2020/6/1 7:00:41)
アルインコ電源 EPS-300M 修理
(2020/6/1 7:00:41)
私の無線歴とともに歩んできた?アルインコの公称30A電源が壊れたのは、前にブログに書きました。電源の故障とは知らず、IC-7300を和歌山病院に送ったのです。 https://nx47.com/modules/xpress/?p=1041

電圧計が振り切れていまして、

24Vを少し超えてしまっています。じゃあ、デコデコ使えばいいじゃん!
そういうわけにもいかず、ヤフオクでジャンク処分するにも重たいものだし、やはり長年の愛着があるわけでもなく、いやいや・・・・
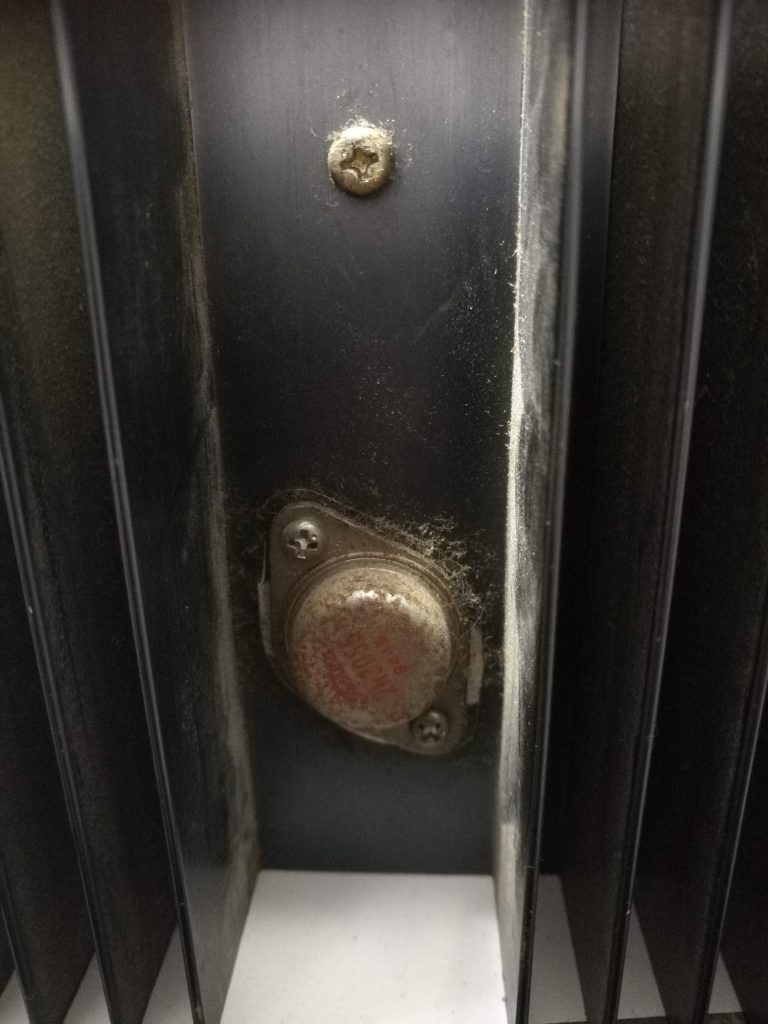
放熱板にこの2N3055というトランジスタが4個付いていて、とりあえず全部取り替えます。
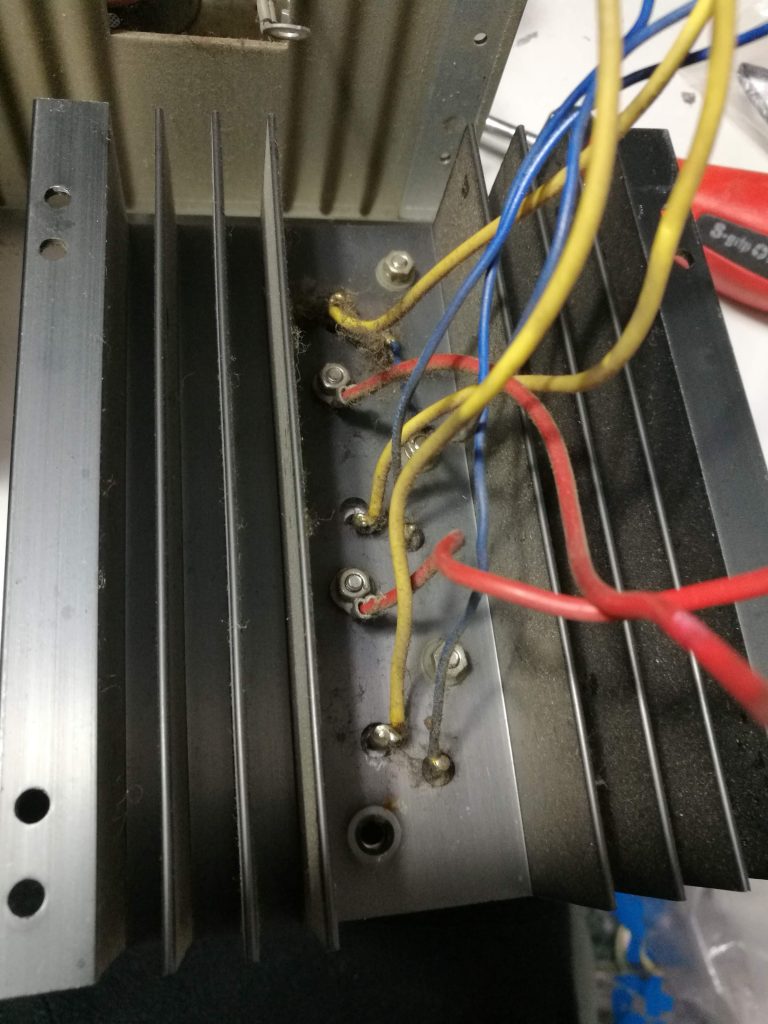
結構、思ったより、大変な作業になりましたが、そこそこ楽しい。
が、相変わらず電圧計は振り切ってしまいました。ガックリ
次に目をつけたのは、
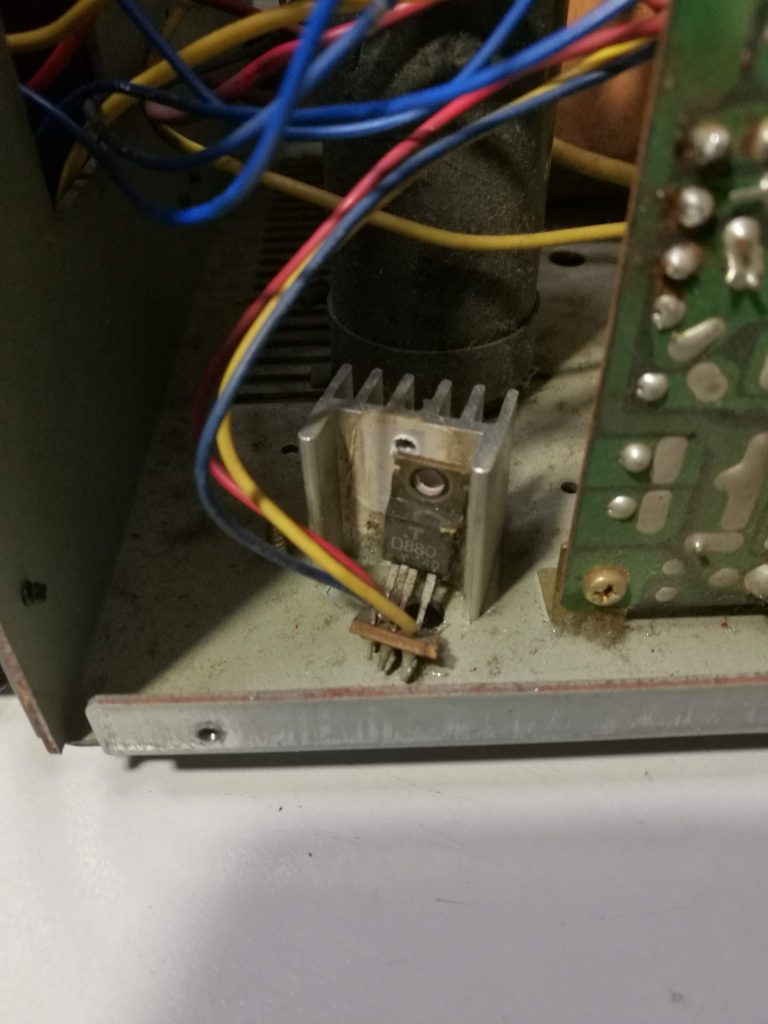
画像は、ネジを取って交換直前の2SD880です。放熱板に取り付けられているのに、全然熱を発しないのは、お前おかしいよ、と交換します。
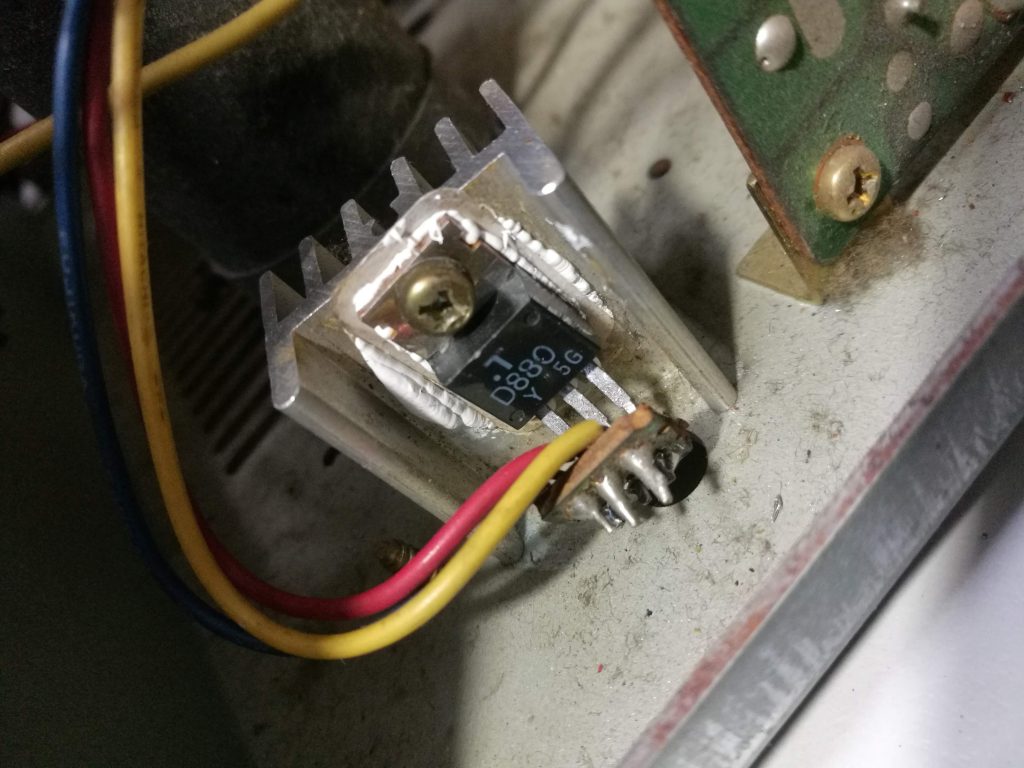
高官官僚、おいおい、交換完了です。

修理できました。さて、いつまで私の無線ライフに付き合ってくれるでしょうね。