無線ブログ集
| メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示

 アマチュア無線局 JO1KVS
(2025/11/18 10:35:52)
アマチュア無線局 JO1KVS
(2025/11/18 10:35:52)
現在データベースには 797 件のデータが登録されています。
 最近の免許や無線局の手続きの変換がよく解る
(2025/3/14 0:00:00)
最近の免許や無線局の手続きの変換がよく解る
(2025/3/14 0:00:00)
https://www.hamlife.jp/2025/03/12/jarl-jaia-jard-sitecheck/
これ、指摘がどうのこうのは別として、知識の確認として勉強になった。
CBT方式の試験とか、講習会の種類とか費用とか。
電子申請もシステムがガラッと変わったことは知ってたけど名前が少し変わってたこととか。
書かれてなかったけどハムショップでは講習会の割引クーポンくれることもあるね。これはもらわないと損だ。
これ、指摘がどうのこうのは別として、知識の確認として勉強になった。
CBT方式の試験とか、講習会の種類とか費用とか。
電子申請もシステムがガラッと変わったことは知ってたけど名前が少し変わってたこととか。
書かれてなかったけどハムショップでは講習会の割引クーポンくれることもあるね。これはもらわないと損だ。
 最近の免許や無線局の手続きの変換がよく解る
(2025/3/14 0:00:00)
最近の免許や無線局の手続きの変換がよく解る
(2025/3/14 0:00:00)
https://www.hamlife.jp/2025/03/12/jarl-jaia-jard-sitecheck/
これ、指摘がどうのこうのは別として、知識の確認として勉強になった。
CBT方式の試験とか、講習会の種類とか費用とか。
電子申請もシステムがガラッと変わったことは知ってたけど名前が少し変わってたこととか。
書かれてなかったけどハムショップでは講習会の割引クーポンくれることもあるね。これはもらわないと損だ。
これ、指摘がどうのこうのは別として、知識の確認として勉強になった。
CBT方式の試験とか、講習会の種類とか費用とか。
電子申請もシステムがガラッと変わったことは知ってたけど名前が少し変わってたこととか。
書かれてなかったけどハムショップでは講習会の割引クーポンくれることもあるね。これはもらわないと損だ。
 音声からの和文モールス自動送信
(2025/3/13 8:26:15)
音声からの和文モールス自動送信
(2025/3/13 8:26:15)
喋ると和文モールスの符号を打ってくれるそんな機能も出来ちゃいますね。既にキーボードで文字を打てば符号を打ってくれるアプリはありますし。自分でコピペすれば出来るので、半自動にはなってますね。
すべて自分の技量で送受信してこその電信ですが。(笑)
そういえばWindowsが95だか98くらいの頃、盛んに音声から文字に変換するソフト、ヘッドセット付きで売られてましたね。最近はあまり聞かない...
すべて自分の技量で送受信してこその電信ですが。(笑)
そういえばWindowsが95だか98くらいの頃、盛んに音声から文字に変換するソフト、ヘッドセット付きで売られてましたね。最近はあまり聞かない...
 音声を文字に変換するアプリで
(2025/3/12 0:00:00)
音声を文字に変換するアプリで
(2025/3/12 0:00:00)
前回のブログ記事は音声を文字に変換してくれるアプリで下書きを書きました。話して文を書いたのは初めてですが、全然うまくいきません。文字の変換精度は問題ないんです。なんかこう文書って書くスピードで考えていく感じじゃないですか。声で書くのはスピード感が合わない。
口述筆記って忙しい人とか助手の居る作家さんとかもやってるみたいだけどよく出来るなぁ。YouTuberの人達も流暢に話しているけど台本先に練っているのかな?
無線の交信ならいくらでも話せるんだけど、ブログ書くの、声でやるの凄く難しかった。(笑)
口述筆記って忙しい人とか助手の居る作家さんとかもやってるみたいだけどよく出来るなぁ。YouTuberの人達も流暢に話しているけど台本先に練っているのかな?
無線の交信ならいくらでも話せるんだけど、ブログ書くの、声でやるの凄く難しかった。(笑)
 オプティメイト7セレクトで車を充電
(2025/3/11 2:05:19)
オプティメイト7セレクトで車を充電
(2025/3/11 2:05:19)
先週の土曜日、八王子では結構雪が降った日(全く積もりませんでした)。
先日買ったオプティメイト7セレクトで車のバッテリーを 充電してみることにしました。
バッテリーは車につないだままの状態で。うちの車は立体駐車場の中に入っているので、家からのコンセントで充電することができません。ポータブル電源を車のそばに持っていくことを考えましたが、いくら立体とは言えボンネットを開けてバッテリーに充電器をつないだまま、何時間か放置しておくのは不安です。
バッテリー、無線用に太めのコードで車内に引き込んだ配線、いわゆるバッ直があるのでこれを利用し、車内から充電してみることにしました。この配線、アンダーソン端子で昇圧器につないでいるのでそこで切り離せばOKです。バッ直コードのヒューズは30アンペア。充電器の出力は最大10アなので問題ありません。
ポータブル電源の最大出力は600Wあり、充電器は最大240WでこちらもOK。ポタ電の容量は大きくないのでもし車のバッテリーが腹ペコだとポタ電が先に切れてしまうことが心配でした。
車のバッテリーは寒いせいか元気がいまいちで、先日の12ヶ月点検では元気度が50%と診断されてしまいました。その後長い時間乗ったりして、自前のバッテリーテスターではgood判定出てるのですが、果たしてこのオプティメイト7はどのような診断結果を出してくれることでしょうか?
ポータブル電源と充電器を車内に持ち込み、抜直のコードに充電器をつなぎ、そして充電器をポータブル電源につなぎ電源をオンにします。 充電が始まった時はバッテリー残50%以下のランプがつきました。 すぐに75%以下のランプに切り替わりました。ポタ電の消費電力は70Wくらい。ガンガン充電するステージでは無い感じ。立体駐車場なので長居は出来ず、すぐに降りて車を地下に下ろし、そのまま数時間放置します。3時間経ってポータブル電源の残を確認しに行きました。オプティメイトの表示はgoodランプ。取り敢えずバッテリーは致命的なレベルではない事は確認出来ました。ポタ電の残はまだたくさん残っていて、あまり充電しないで済んだ模様です。ポタ電、別のに積み替えて、再び充電を開始、翌朝まで放置してみることにしました。この充電器は、休んで監視しつつ、様々なモードを駆使してバッテリーが元気になるようにしてくれます。それを期待して。 24時間以上何日もずっとつないだままでも良い充電器なのです。(そこが良いところ) 翌日の寒い朝にエンジンを始動てみました。 めちゃくちゃ元気、というほどではなかったですが、普通にセルが回り問題なくエンジンがかかりました。 まあこんなもんかな。
週末しか乗らない車なので、たまにこれをやってあげればバッテリーの持ちは少し良くなるかなと思います。
ポータブル電源と充電器を車内に持ち込み、抜直のコードに充電器をつなぎ、そして充電器をポータブル電源につなぎ電源をオンにします。 充電が始まった時はバッテリー残50%以下のランプがつきました。 すぐに75%以下のランプに切り替わりました。ポタ電の消費電力は70Wくらい。ガンガン充電するステージでは無い感じ。立体駐車場なので長居は出来ず、すぐに降りて車を地下に下ろし、そのまま数時間放置します。3時間経ってポータブル電源の残を確認しに行きました。オプティメイトの表示はgoodランプ。取り敢えずバッテリーは致命的なレベルではない事は確認出来ました。ポタ電の残はまだたくさん残っていて、あまり充電しないで済んだ模様です。ポタ電、別のに積み替えて、再び充電を開始、翌朝まで放置してみることにしました。この充電器は、休んで監視しつつ、様々なモードを駆使してバッテリーが元気になるようにしてくれます。それを期待して。 24時間以上何日もずっとつないだままでも良い充電器なのです。(そこが良いところ) 翌日の寒い朝にエンジンを始動てみました。 めちゃくちゃ元気、というほどではなかったですが、普通にセルが回り問題なくエンジンがかかりました。 まあこんなもんかな。
週末しか乗らない車なので、たまにこれをやってあげればバッテリーの持ちは少し良くなるかなと思います。
 いろはにほへと ちりぬるを
(2025/3/10 12:20:26)
いろはにほへと ちりぬるを
(2025/3/10 12:20:26)
この続きは知りません。どの世代までこれ暗記してるのだろう。昔のかなの順番です。
欧文の符号と和文の符号、少し飛ぶところとかあるけれど、ほぼこの順番です。
い Aろ は Bに Cほ Dへ Eと ち Fり Gぬ Hる を J
さすがに ゛はIが譲れませんね。
これずっとやっていくと、本当にこの順です。
大先輩にはあたりまえの知識ですが、知ってましたか?
欧文の符号と和文の符号、少し飛ぶところとかあるけれど、ほぼこの順番です。
い Aろ は Bに Cほ Dへ Eと ち Fり Gぬ Hる を J
さすがに ゛はIが譲れませんね。
これずっとやっていくと、本当にこの順です。
大先輩にはあたりまえの知識ですが、知ってましたか?
 ブログ開設から7000日
(2025/3/8 4:06:52)
ブログ開設から7000日
(2025/3/8 4:06:52)
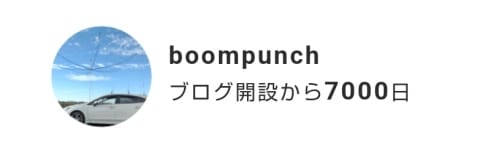
ブログ開設から7000日だそうです。年数だと19年ちょっと。無線熱は変わらない。これが自分の平熱ってことなんでしょう。
読んでいただきありがとうございます。
このブログのシステムが続いていてくれているのはありがたい。栄枯盛衰の激しい世界ですし。有料会員になると本に出来るサービスがあるそう。ちょっと興味ありますね。ある日突然全部消える時が来ても、手元には残る。
最初の頃のハンダコテの話とか懐かしいです。
今後ともよろしくお願いします。おめでとうのお気持ちは、下のブログランキングバナーのクリックで(笑)
 海外の工具 大小はあっても中は?
(2025/3/7 12:37:23)
海外の工具 大小はあっても中は?
(2025/3/7 12:37:23)
聞いた話だけれども、日本人ってソケット式のハンドツールって、9.5mm角のサイズが標準的ですよね。いわゆる3/8inchサイズ。手で回すネジ類の大きさ、力加減とのバランスも良くて、取り回しも良い。ところが欧米はちょっと違っていて、1/4インチ角、パワー要るなら1/2インチ角、この二つのどちらか、と言う考え方なんですって。大か小。中は無いの?って感じですね。
一般の人が使う工具、1/2インチ使うことって車のホイールナット回す時くらいしかないですよね。むこうは体も大きくてパワフルな体格の人多いから良く使うのかなぁ。
日本人はちょうどいい、と思うサイズひとつでなんでもやるのが好きですね。1/4を積極的に使う人は少ない。F1の海外のチームの整備士さん1/4結構使うそうです。工具の頼りなさがオーバートルクを防ぐのだとか。そう言えばエンジンのチューンの名人は、ダメじゃないギリギリの緩さで締めるっていう噂です。もちろん適所に合わせて。
確かにインチ単位だと1/4がひとつの単位です。4つで1になる。ハーフとかクォーターとか、それです。むこうの人はぐるっと円を一回りで1と考えます。半周をハーフ、その半分をクォーター。1を10で区切らない。半分の半分の、そのまた半分、みたいに考えます。10進法とはちょっと相性が悪いです。
テニスも得点は15-30-40-Game ですね。60で時計が一回り。半分が30、その半分が15。40は、45と言うのが面倒だから40と言っているだけで実は45です。円に針をつけて回して表示していたそうです。一年が12ヶ月。4で割れる数。これもそう言うことです。
日本人には馴染みがないけどなる程ですね。2500円札、あってもおかしくないんですけど、日本人には馴染みませんね。
一般の人が使う工具、1/2インチ使うことって車のホイールナット回す時くらいしかないですよね。むこうは体も大きくてパワフルな体格の人多いから良く使うのかなぁ。
日本人はちょうどいい、と思うサイズひとつでなんでもやるのが好きですね。1/4を積極的に使う人は少ない。F1の海外のチームの整備士さん1/4結構使うそうです。工具の頼りなさがオーバートルクを防ぐのだとか。そう言えばエンジンのチューンの名人は、ダメじゃないギリギリの緩さで締めるっていう噂です。もちろん適所に合わせて。
確かにインチ単位だと1/4がひとつの単位です。4つで1になる。ハーフとかクォーターとか、それです。むこうの人はぐるっと円を一回りで1と考えます。半周をハーフ、その半分をクォーター。1を10で区切らない。半分の半分の、そのまた半分、みたいに考えます。10進法とはちょっと相性が悪いです。
テニスも得点は15-30-40-Game ですね。60で時計が一回り。半分が30、その半分が15。40は、45と言うのが面倒だから40と言っているだけで実は45です。円に針をつけて回して表示していたそうです。一年が12ヶ月。4で割れる数。これもそう言うことです。
日本人には馴染みがないけどなる程ですね。2500円札、あってもおかしくないんですけど、日本人には馴染みませんね。
 ポータブル電源 suaokiはもうない
(2025/3/6 0:00:00)
ポータブル電源 suaokiはもうない
(2025/3/6 0:00:00)
ポータブル電源が流行りだした頃、盛んだったsuaokiというメーカー、もう無いんですってね。うち、大小二台あるんだけど。壊れてないからいいけれど。ある方のブログでAC急速充電アダプタ壊れ、シガーソケットからのやつも壊れ、充電できなくなって四苦八苦している話が出てました。
太陽光発電のパネルが直でつなげられるポタ電なら求められている電圧以上の電気を加えればあとはポタ電がやってくれるので結構適当でOKなのです。コネクタも変換コネクタセットみたいのがAmazonとかで売られているのでなんとかなります。
重いけど1000W出力タイプなので停電に備えても役に立ちます。電子レンジも1分は動かせますから。
ノイズ出るので無線には使いにくいんだな。どのポタ電も結構出る。ほとんど出ないよ、というやつは無線界の方でどんどん紹介してあげるといい。我らはそれを選ぶから。
太陽光発電のパネルが直でつなげられるポタ電なら求められている電圧以上の電気を加えればあとはポタ電がやってくれるので結構適当でOKなのです。コネクタも変換コネクタセットみたいのがAmazonとかで売られているのでなんとかなります。
重いけど1000W出力タイプなので停電に備えても役に立ちます。電子レンジも1分は動かせますから。
ノイズ出るので無線には使いにくいんだな。どのポタ電も結構出る。ほとんど出ないよ、というやつは無線界の方でどんどん紹介してあげるといい。我らはそれを選ぶから。
 車のバッテリー充電器 オプティメイト7セレクト
(2025/3/5 0:00:00)
車のバッテリー充電器 オプティメイト7セレクト
(2025/3/5 0:00:00)
車のバッテリー充電器買いました。
どうしても欲しくなってしまって。
実はこの冬、なんかエンジンの始動の時にセルの元気が無い。
12ヶ月点検のときもバッテリーの元気度50%と診察されてしまいました。
もっと乗ればよいのでしょうが・・・
よろしくない傾向です。バッテリーそんなに古くないのに・・・
(この土日は暖かかったせいか、先週もそこそこ乗ったからかまあまあ元気でした。)
我々って電気の専門家じゃないですか。
バッテリーの充電器なんて、無線機用の安定化電源と比べたらたいしたものじゃない、って考えちゃいますよね。
少し高めの電圧かけて、電流制御していればいい、みたいな。
ただ、これだとつきっきりになって監視していないといけない。
世の人はつないだら放っておくしか出来ないから、専用の製品があるのでしょう。
しかもよい充電器はそれなりにいろいろやってくれている。
パルス充電、っていうのは聞いたことがありますよね。
充電中に電圧をパルス状に変化させて、バッテリーをくすぐるわけです。
その波形、電圧も様々。
なんでこんな刺激を与えるかと言うと、サルフェーションの除去、とか、活性化とか?を狙っているようです。
充電中にもいろんなモードを順に実施して、よりよい充電、バッテリーの回復を目指すものが開発されてきました。安価なものは単に満タンにするだけ、というものも多いですが。
今回導入したのはオプティメイト7セレクトという充電器です。(セレクトじゃないのもあるので要注意)
お値段は結構します。
急速充電といっても最高10A。車の充電器としてはそれほどガンガンでもない。
どちらかというといたわり系の充電器です。
何が凄いって、バッテリーをいろんなステージで検診、観察して、診断結果に応じて必要なモードで充電していく。充電休んで電圧保持能力とか観察して、またその結果次第で必要な措置を施していく。繋ぎっぱなしにしておいてもそれを長期に渡って実施してくれる。過放電の弱りに弱ったバッテリーでも回復を試みてくれる。車から外してきたバッテリーだと22Vでのサルフェーション除去もやってくれる(車についたままだとこの機能は発動しない。車の電子機器が壊れちゃうから。)。つまりその辺の充電器のパルス充電って、健康維持では効いても健康回復としてはイマイチってことですね。
それらが全自動なんです。
実際手元の7ahのシールドバッテリーにつないでも、それなりに労って充電してくれる。バッテリー熱くならない。きちんと相手を見てモードを発動してくれている感じです。
車、安全な車庫に停められる人なら、乗らない時はずっとつないでいたい充電器。現にそうしておくと、もう何年も何年もバッテリーが元気に使えるそうで、充電器のお値段楽勝で元が取れるとか。
車大好きで車数台持っている人は、どうしてもバッテリーあがり起こしがちですよね。そういう方にも人気商品だそうです。
うちは団地の立体駐車場なのでつなぎっぱ出来ないんですが、休日にポータブル電源と合わせて出かけた先で数時間充電してみたいなぁと思っています。
ベルギー製。テックメイト社。各自動車メーカーさんも正式に採用していて、柄の異なるOEM製品も出している信頼のおけそうなメーカーです。
ちょっと楽しみです。
execution time : 0.082 sec
