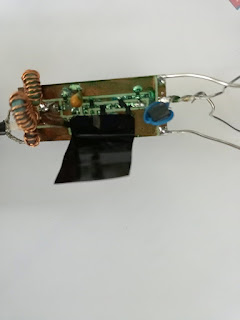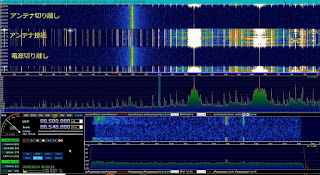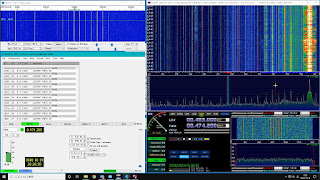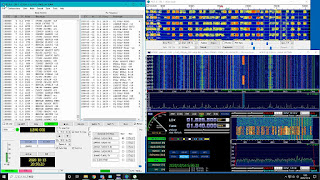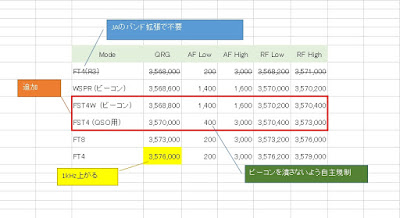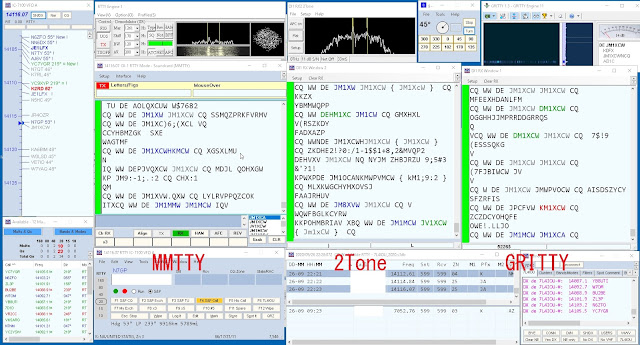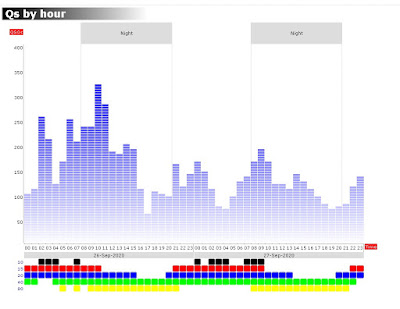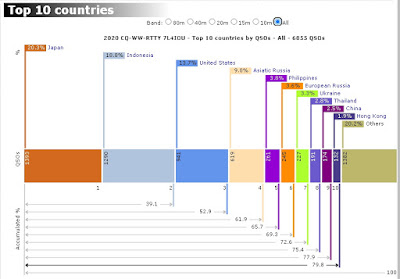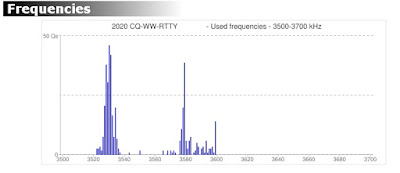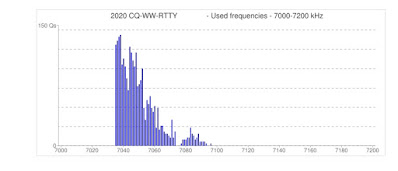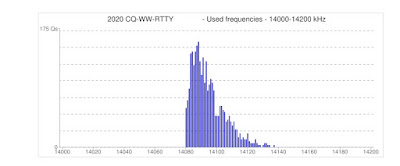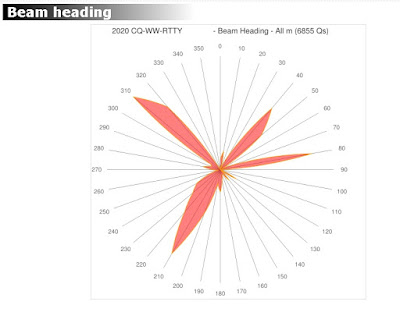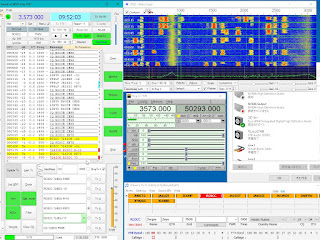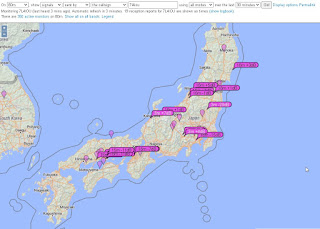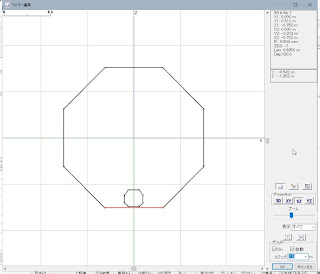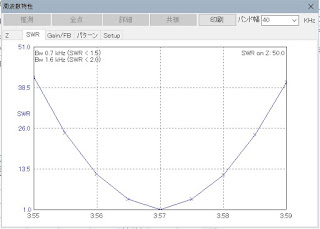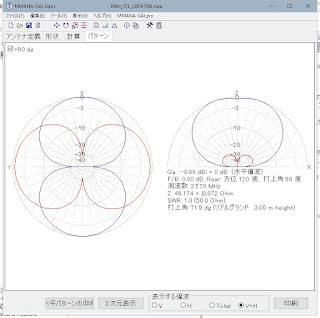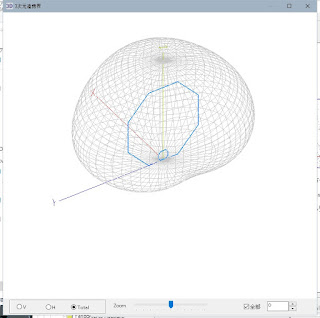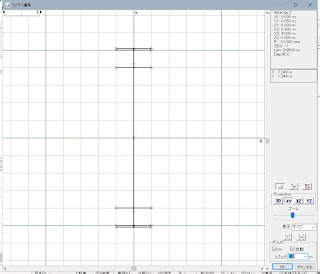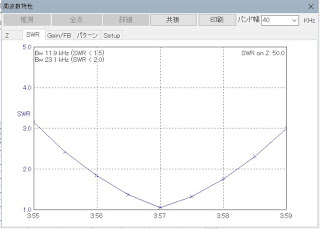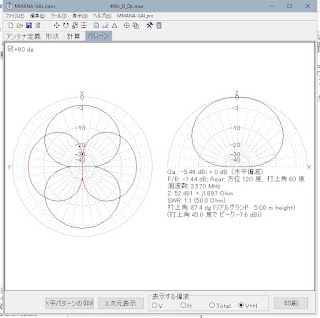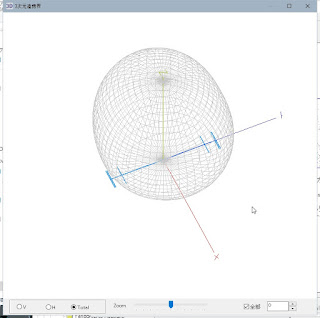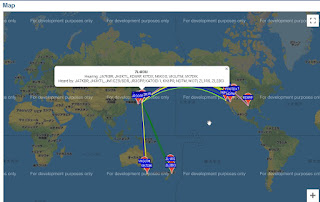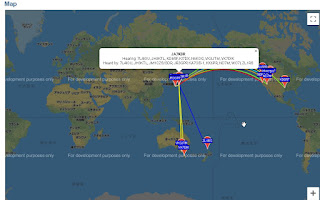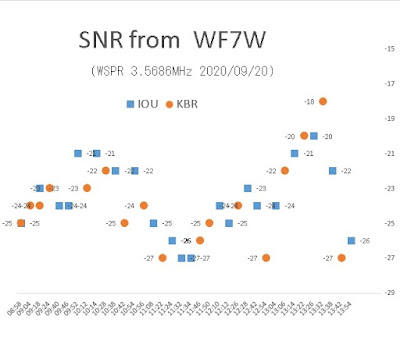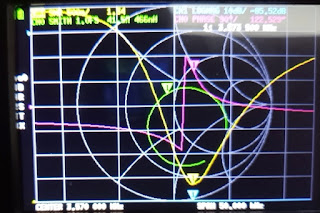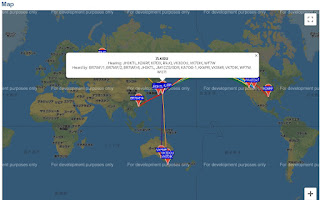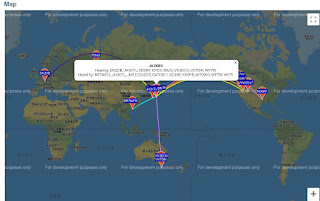無線ブログ集
| メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示

 7L4IOU
(2025/11/18 10:35:55)
7L4IOU
(2025/11/18 10:35:55)
現在データベースには 305 件のデータが登録されています。
 今週末はJARTS WW RTTY Contest
(2020/10/15 20:20:01)
今週末はJARTS WW RTTY Contest
(2020/10/15 20:20:01)
de 7L4IOU
早いもので、今週末はJARTS WW RTTYの開催となります。
2020年のルールでは、バンドプラン違反について以下のように明確化しました。
-----------------------------
バンド:3.5, 7, 14, 21, 28MHz
※バンドプランを遵守すること。
※国際ビーコン周波数 14100kHz +/- 1kHzは、コンテスト運用に使用しないこと。
※上記に違反する交信は無効とする。また、上記に違反する10分間以上ランニン
グ、もしくは10QSO以上の交信を行った局は失格とする。
(バンドプランから逸脱した交信は無効とする。)
-----------------------------
従来、3.535~3.575MHz、7.045~7.100MHzなどJA同士のQSO禁止区分でのQSOは
無効とし、「ついウッカリ」を超えると思われる局には、個別にご注意を喚起してきました。
電波法の遵守は言うまでもありませんが、JARTSコンテスト委員会として、正直者が損をしないような「公正の確保」も大変重要と考えての改訂です。
今年は、10以上の違反QSOや、14,100kHz ±1kHzでの10分間以上のランニングは、機械的に失格となりますので、くれぐれもご注意ください。
コンディションは少し下がり気味ですが、宇宙天気 <http://swnews.jp/>は、週末にかけて「概して静穏」のようです。 http://swnews.jp
奮ってご参加ください。
----------------------------
名 称:JARTS WW RTTY CONTEST
日 時: 10月17日 09:00 ~19日08:59 JST
周波数:3.5~28MHz
※バンドプラン遵守すること。
※国際ビーコン周波数 14100kHz +/- 1kHzは、コンテスト運用に使用しないこと。
※上記に違反する交信は無効とする。また、 上記に違反する10分間以上のランニ
ング、もしくは10QSO以上の交信を行った局は失格となる。
モード:RTTY
交信相手:JA局を含む全世界の局
部 門
SOHP: シングルOP,オールバンド,ハイパワー (出力制限無し)
SOLP: シングルOP,オールバンド,ローパワー (出力100W以下)
MO:マルチOP,オールバンド (マルチTX可,出力制限無し)
※すべての部門でDXクラスタを使用できる.
ナンバー:
・シングルOP局は,RST+オペレータの年齢 (YLは00も可)
・マルチOP局は,RST+使用するコールサインの免許人の年齢 (クラブ局の場合
は99)
ロ グ:キャブリロ形式のログを電子メールに添付して送信する.
・ログのファイル名は参加したコールサイン+拡張子とする. [例,JA1YCQ.
cbr]
・メールの表題には参加したコールサインを入れる. [例,Subject: JA1YCQ]
・運用周波数をkHz単位で記載していないログは,表彰の対象とならない.
アドレス: log@jarts.jp
締 切:10月31日(必着)
※ログ提出の3日後に,ホームページのログ提出局リスト(Submitted Logs
2020)にコールサインが掲載されるので確認すること.
主催者ホームページ: http://www.jarts.jp/
 MiniWhip用バイアス・ティーの検討-2
(2020/10/14 19:44:57)
MiniWhip用バイアス・ティーの検討-2
(2020/10/14 19:44:57)
バイアス・ティーを見直したミニホイップですが、
どうしてもノイズが残って「使い物になるのかな?」と心配でした。
まずは、電圧を上げるための放熱です。
クールスタッフを貼り付けました
ペットボトル内の対流が、あまり期待できないのですが、当座できるのはこんなところです。
久しぶりの点検がてら、ルーフタワーのステーに引っ掛けました。
シャックに戻って、供給電圧をいじっている内、電源がかなりノイズっぽいのに気が付きました。
菊水の古い実験用電源です
バイアスTもどきは、直下型プリアンプなどのためいくつか作っていました。
その中に、LM317で電圧を可変できるのがあったことを思い出しました。
コアの下の白い□がボリューム
例によって、鮟鱇の吊るし切り方式ですが(そろそろ鮟鱇が美味い季節ですね・・・)
VHF用の小さいガルバニックアイソレータをBN-202-73に交換し、
RFCを緑コアに取り替えました。
これに、昔のトランス式ACDCコンバータから12V(無負荷時は約20V)を供給しました。
菊水をキャプチャーし忘れたのですが、改造後にアンテナと電源を交互に切り離した様子です。
電源からのノイズ混入はなくなったようです
物は試しと、630mと2200mをモニターしてみました。
WSPR NetやRBNに上がるレポートを見ると、まだまだ足元にも及びませんが何とか見えるようになりました。
また、けさの160mは賑わってましたね。
残念ながら、MiniWhipではR5AJくらいしか見えませんでした。
 噂のWSJT-X 2.3.0 rc1 (新モードFST4とFST4W)の公開
(2020/10/1 18:18:02)
噂のWSJT-X 2.3.0 rc1 (新モードFST4とFST4W)の公開
(2020/10/1 18:18:02)
新モードFST4とFST4Wで関心が集まっていた、WSJT-Xの2.3の rc版が公開されました。
4-GFSK変調を使用したモードで、幾つかのサブモードがありますが、ほぼ理論上の限界に近づいているようです。
クイックスタートガイド
https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FST4_Quick_Start_jp.pdf
特に1800秒(30分)モードは凄いですね。
時間はかかりますが、-43dBとのこと。
160mのW西海岸は、ホイップでもできそうです。
さっそくインストールしてみましたが、
運用周波数は、136kHZ, 474kHz, 1.8MHzのローバンドしか設定されていないようです。
160mはアンテナがありません。orz
出来れば、80mでも使ってみたいものですね。
頭の体操をしてみました。
 CQ WW RTTY Contest - 2 複数解読
(2020/9/29 14:49:46)
CQ WW RTTY Contest - 2 複数解読
(2020/9/29 14:49:46)
CQ WW RTTYに参加しました。
久しぶりに10時間ほど運用し、重複込みで150局ほどのQSOでした。
Band QSOs Pts ZN Cty SP Pt/Q
3.5 5 5 1 1 0 1.0
7 33 68 8 8 6 2.1
14 85 218 11 15 11 2.6
21 34 89 9 11 0 2.6
Total 157 380 29 35 17 2.4
なかなかコンディションが上がってこないですね。
今回は、南米とアフリカは見つけられず、4大陸に終わりました。
解読は、MMTTY, 2TONE, GRITTYを併用しました。
オープンすれば、北米の東海岸あたりに効果を発揮します。
が、今回の出番は、グランドウエーブと反射波の境目あたりで面白い解読例がありました。
「どれか一つ」と言われれば、MMTTYの一択です。
「もう一つ、良いよ」と言われれば、GRITTYでしょうか?
実は、
例の80M STLを試してみようと思い、日曜の夕方FT-817でJA7KBRを急遽セットアップしました。
こちらは、FSKがないのでAFSK送信になるのですが、2TONEのマニュアルを見たら、キレイな変調の効能書きに目が止まり、結局3~4時間ほども嵌まってしまいました。hi
そちらはまた後で・・・
 CQ WW RTTY Contest - 3 スキマーの捕捉状況
(2020/9/29 13:06:31)
CQ WW RTTY Contest - 3 スキマーの捕捉状況
(2020/9/29 13:06:31)
コンテスト前夜にセットしたRTTYスキマー、ダウンすることもなく終了まで稼働しました。
この間に補足したデータを SH5で処理してみました。
解読できた局と全てQSOできたとしたらと云う、究極のタラレバです。
ご笑覧ください。
解読数等
・開始時刻:26-Sep-2020 00:00
・終了時刻:27-Sep-2020 23:59
・稼働時間:47:59
・QSOs:6,855 <--- 解読数
・Dupes:5,675 (82.79 %)
・Unique callsigns:745
※壊れたコールがかなりあります。実数は720くらいでしょう。
・Countries:65
Qs by hour
我が家では、初日の方が良く見えていたようです。
アフリカは見えませんでした。
Top 10 countries
どのバンドもインドネシアの局がアクティブでしたね。
Qs by band
バンドの比率です
なかなかハイバンドが開かないですね。
周波数の分布
80m
Wは、かなりの局が3530あたりまで降りてくれました。
3.575-3.580、3.599-3.602辺りは、対EUの窓になってきました。
3.531の国内FT8、本当はデジタルセグメントの下端が良いのですけどね・・・
40m
7.074のFT8は流石にどなたも出ていませんでした。
7.041もJAは避けるのですが、近隣のDXはかなり見えていました。
なお、RTTYに不慣れな方でしょうか。
7.045から上でJA同士でQSOしているのを見かけました。
JARTSでは、減点や失格の対象になるので、注意が必要です。
20m
このバンドは、14.100のIBPビーコンが要注意です。
YBやEUでランニングしている局が見えていました。
なお、ほとんどのスキマー局は、
14から上のバンドでは、80kHzから上を解読するように設定しているようです。
ちょっと残念なのは、
噂では、14.070より下でZF1AとQSOするJAが何局か居られたとか・・・
つまらない事で後ろ指を差されないように、気をつけたいものです。
Beam heading
全期間をとおしてのビーム方向です。
YB局は増加の一途を辿っているので、瞬時にビームを反転できる巻き尺アンテナは有利ですね。
アンテナトラブル
スキマーは、RedPitaya(SDR)とナガラのトラップ・バーチカルを使っています。
感度が今一つなので、しばらくぶりにSWRを確認したところ、かなりズッコケていました。
どうも、一番下の28MHz阻止用トラップが故障しているようです。
撓りではなく曲がり
実は、メーカーからアンテナにステーを取らないように注意されていました。
が、去年の台風対策で緩くステーを取ったままにしていました。
そのあたりが原因かもしれません。
拙いな~
 CQ WW RTTY Contest と Skimmer設定
(2020/9/25 11:18:31)
CQ WW RTTY Contest と Skimmer設定
(2020/9/25 11:18:31)
明日(土曜日)の午前9時から月曜日の午前9時まで、48時間にわたってCQ World Wide RTTY DX Contestが開催されます。
日本語訳ルール: https://www.cqwwrtty.com/rules/CQWWRTTY_Rules_2020%20Japanese.pdf
このコンテストは年間を通して、参加者が一番多いRTTYコンテストです。
デジタルに一本化されましたが、RTTYのDXCCを追いかけている局には欠かせないイベントです。
DXCCもアワードも追いかけていませんが、とにかくRTTYのQSOが楽しい私には、ピロピロ音が祭囃子のように聞こえて、他のことは手につかなくなります。hi
で、昨晩寝床に入って、オーバーヒートでRTTYスキマーがダウンしていたのを思い出しました。
起き出して、おっとり刀で再起動しようとしたのですが・・・
PCが動きません。ソフトや設定値が回収できなくて、がっくり。
結局、別のPCに入れることになりました。
OSのインストールやアップデートに加え、RedPitayaやスキマーサーバーの設定はすっかり忘れてしまい、四苦八苦。何とか動き出した頃は、とっくに日付が変わってました。
しかし、朝見ると、たったの3つしかCQを補足していません。「オイオイ」とため息が出ました。
ふと気を取り直して、RBNにアクセスして見ると・・・
他の皆さんも同じでした。ヤレヤレ。
JAのRTTYスキマー捕捉状況: http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=50628
それにしても、デジタルモードの代名詞だったRTTY。
日常のアクティビティはすっかりシャッター通り化して、週末のコンテストモードになったのを実感させられました。
- CQ WW RTTYの概要 -
名 称:CQ World Wide DX RTTY Contest
日 時:9月26日09:00~28日08:59
周波数:3.5~28MHz
モード:RTTY
交信相手:JA局を含む全世界の局
※シングルOPアシステッドとマルチOP部門は,クラスター等を使用できるがセ
ルフスポットは禁止.
ナンバー:RST + CQゾーン
※W本土およびVEの局は,RST + CQゾーン+ 州またはプロヴィンス .
ロ グ:Cabrillo形式のログを提出用ウェブページからアップロードする.
締 切:10月3日08:59JST必着 (コンテスト終了後5日)
主催者URL: https://www.cqwwrtty.com
 BATAVIA FT8 CONTSTの結果発表
(2020/9/24 11:48:35)
BATAVIA FT8 CONTSTの結果発表
(2020/9/24 11:48:35)
8月初めに開催された BATAVIA FT8 CONTSTの結果が発表されました
https://batavia-ft8.com/final-results/
さっそくアワードをダウンロードさせていただきました。
何方かがコメントしていましたが、
Webページはじめとても良く出来たシステムで、スキルの高さが窺えます。
何方が作ったのでしょうね?
これで通常以外のコンテスト用QRGが設定されていれば100点満点です。hi
来年が楽しみです。
 80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) - 4
(2020/9/24 11:17:30)
80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) - 4
(2020/9/24 11:17:30)
22日の夜、WSPRの合間にFT8を覗いたところ、W6のCQが見えていました。
たぶん届かないだろうと思って5Wくらいで呼んだところ、-20が返ってきました。
しかし、残念ながらあとが続かなくて尻切れに終わっていました。
後で気付いたのですが、時計も1秒近くズレていました。orz
と云う訳で、QSOにトライしてみたいと思い、昨晩はIC-7100に繋ぎ変えました。
今回使用したLDF4-50Aの規格は、
dc Test Voltage 4000 V
Jacket Spark Test Voltage (rms) 8000 V
との事、耐圧は大丈夫でしょう。
接続も、アーク対策として、同軸両端の直結ではなく、
1.6mmΦのIV線でジャンパーしていたので、出力は100WもOKでした。
昨夕は、南米方向が良いようで、皆さん盛んにVP8LPをコールしていました。
が、建物の影でもあり全く見えませんでした。
北米は?と思ったのですが、改めて眺めると常連の局は意外にQSO済で、良い相手が見つかりません。
そのうち RC0CCのCQが-2dBで見えたので、コールしてみたところ
レポートは -11dB \(^o^)/
と云う訳で、同軸STLでの1st QSOとなりました。
このあとにUT2XQからも応答があったのですが、73は微妙でした。
これは今朝ですが、PSK Repoeterでも、国内には充分な強さで届いているようです。
バンドの拡張はご存知でも、ただし書きの範囲外という認識は無かったようです。
 80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 3
(2020/9/24 1:43:37)
80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 3
(2020/9/24 1:43:37)
飽きもしないで、チマチマとやっています。
LDF4-50A同軸STLとTA-51jrをシミュレーションしてみました。
メーカの資料によると、LDF4-50Aのシールドの直径は13.97mmとの事です。
が、MMANAでこの蛇腹(コルゲート)を表現する方法が分からないので、13mmの半分、6.5mmの銅パイプとして設定しました。
コンデンサの位置
芯線とシールド間の容量は75.8 pF/mとの事で、ケーブル全体がコンデンサです。
ここでは、先日アークした箇所(接続部)をコンデンサの位置と見做す事にします。
彼方此方の資料を見ると、コンデンサの反対側にリンクを設けるケースが多いようです。
しかし、MMANAによるシミュレーションでは、上下左右どの位置にあってもSWRやゲインの差は殆どありませんでした。
なお、コンデンサのQは1000で入力しました。
STLの諸元
・メインループ全周:5.2メートル
・メインループ・エレメント半径:6.5ミリ
・同調用コンデンサ:398pF (ケーブル容量)
・リンクループ全周:0.65メートル
・リンクループ・エレメント半径:1.0ミリ
実物との違い
同軸の定格キャパシタンス(75.8 pF/m)から逆算すると、全周は5.25メートルとなるので、実物にかなり近い(数センチ以内?)ようです。
他のバンドに応用する場合も、シールドの外径と1メートルあたりのキャパシタンスが分かれば、MMANAのシミュレーションで10Cm以内の誤差に収められるような気がします。
短縮DPの諸元
TA-51jrをイメージして、ワイヤーを編集しました。
ローディングコイルのQは100としました。
・エレメント全長:10メートル
・エレメント半径:10ミリ
・ハット:3本(2メートル長)×2組=6本
・短縮コイル:エンドローディング(67uH, Q=100)
昨晩は少しコンディションが悪かったようです。
同軸STL (2W)
個別のSNRをみると、南側以外は、勝ったり負けたりで、ほぼ同等のようです。
シミュレーションでは3dBくらいSTLのゲインが小さいので、
・短縮Dpの、実物のコイルのQが低い?
・STLの、蛇腹が良く作用している?
・STLの、建物の壁が反射板になっている?
といった辺りの作用で、差が縮んでいるのかも知れませんね。
受信については、STLに軍配が上がりそうです。
受信機の性能差も考えられるので、SunSDRでFT8を同時受信して、同一条件で比較したいと思います。
 80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 2
(2020/9/22 8:20:36)
80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 2
(2020/9/22 8:20:36)
同軸STLと短縮DPの比較、送受信のSNRを捏ね繰り回すとつい嵌まってしまいます。
例えば、WF7Wからもらったレポートです。
この局のQTHは、ワシントン州のPort Angelesというところだそうです。
WSPR NETの自己紹介では、IC7300と80mはDPを使っているようですが、飛びも耳も抜群で、羨ましい限りです。
こちらの日没グレイラインの0858zにIOU(Dp)とKBR(STL)が、-25で同時に届きました。
両方が一番暗くなる1130zに一旦底を打った後、
向こうの日の出グレイラインの1332zにピークに達し、
日が昇った、1400zには消感しました。
開きだしてからは、STLのKBRが-2dBくらい低いのですが、ピークでは殆ど差がないのと、オーブンとクローズがほぼ一緒なのは意外でした。
またSNRだけで見ると、2WとSTLのFT8でも、QSOのチャンスは十分に期待できます。
それにしても、短縮とはいえ全長約10メートルのDpと直径約1.6メートルのループでほとんど差が無かったのは驚きました。
回転半径で言えば、5メートルと0.8メートルです。
そんな訳で、もう1センチほど切り詰めて、3.573MHzに合わせてみました。
使い物になりそうな、SWRが2以下の範囲は3.570~3.580の約10kHzです。
昨晩も両方を動かしてみました。12時間はこんな感じです。
南側を除くと、送受信ともにSTLに軍配が上がるようです。
斜めの屋根が反射板になっている可能性は否定できませんが、悪影響の方が大きいでしょうね。多分。